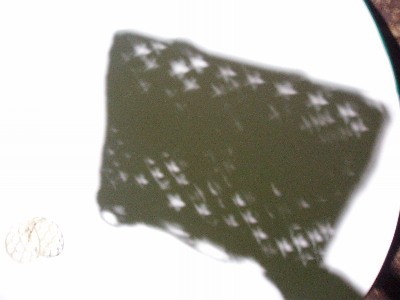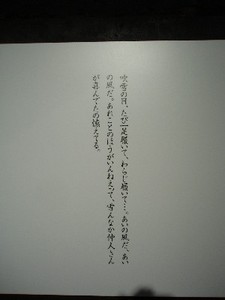好きな作品3 ボルタンスキー
2006年10月15日 大地の芸術祭
クリスチャン・ボルタンスキーは、第1回以降、大地の芸術祭へ継続的に参加しています。
そもそもぼくが前回の第2回で初めて大地の芸術祭をを見に行こうと思ったのも、J.タレルとともにボルタンスキーが出品していると聞いたからです。
二人ともぼくが大好きな作家です。
特にボルタンスキーは、1990年に水戸芸術館での展覧会が素晴らしく、その後、ぼく自身も制作面で影響を受けたことは間違いないと思います。
1990年の展示は、古着のインスタレーションとともに、どこの誰とも知れぬ肖像写真の群像を祭壇のようにして祭り上げ、ライトアップした「モニュメント」「聖遺物箱」シリーズ、ユーモラスで素朴な人形(ひとがた)の切り抜きを蝋燭やライトで壁に映し出す影絵作品など、そのどれもがその場に立ちすくんでしまうような作品ばかりでした。
ボルタンスキーの作品には、そのどれもに「死のにおい」がします。
死といっても、それは残酷な現実をこれ見よがしに突きつけるようなものではなく、不在そのものをそこはかとなく提示するような手法です。
たとえばぼくたちが大正時代の古いモノクロ写真などを見るとき、「ああ、ここに写ってる大人たちは、もうこの世にいないんだ」と思うことがあるのですが、そうしたまなざしが全作品を通じて存在しているように思います。
作者自身、「自らの幼少期の死」を初期の作品のテーマにしているように、(=子どもとしての自分はすでに死んで失われた)
おそらく否応なしに失われたものに対して目がいってしまう性質があるのでしょう。
ボルタンスキーは、観客を泣かせます。
一見、ノスタルジックで感傷的な素材を選び、「我々は日々死んでいく」「我々は常に何かを失っていく」という事実を提示します。
しかし、そこに提示されている素材は、本当に事実に基づいているかどうかは重要でなく、例えば初期作品「10枚のクリスチャン・ボルタンスキーの肖像1946-1964」では、自分自身と無関係の人物の肖像が、それぞれ同年齢の自己として構成されているといった具合です。
要は観る者が共通して持っている過去の記憶を再構成するための素材であればそれでよいという考え方です。
感傷的な作品に感情移入しているように見えて、実はドライで計算づくの制作態度でもあると言えるでしょう。
前回2003年の作品「夏の旅」は、今回と同じ東川小学校を舞台とした大規模なインスタレーションがジャン・カルマンとの合作により展開されました。
この作品は、まさに前述したボルタンスキー節が満喫できる作品でした。
校舎の玄関にぶら下がる無数のスリッパ、枯れた夏草が敷き詰められた理科室、積み上げられた無数の本の山に掛けられた白いシーツ、そして遠く(音楽室と思われる部屋)から聞こえる、在りし日の音楽の授業の音声(廊下が板で塞がれており、遠目にしか教室が見えないが、無人のピアノだけがかろうじて確認できる)、そこでは「兎追いしかの山・・・」など、すこしあざといぐらいのお涙頂戴の選曲がなされている。
これまで「死」や「不在」をテーマにしていたボルタンスキーにとって、大地の芸術祭は、どうしようもないほどドンぴしゃの舞台であることがよくわかりました。
「夏の旅」は文句なく僕の中では2003年のベスト作品でした。
さて、前置きが長くなりましたが、今回の「最後の教室」です。
ここではこれまでとうって変わって、情感めいた手つきが消え、ある意味暴力的といえるほどの大がかりな仕掛けが学校全体に施されていました。
まず、体育館から入ると、床全体に藁が敷き詰められ、むせるような匂い。
高い天井から無数の裸電球が吊られ、それらが扇風機の風で揺らいでいる。
壁面には、雪降りをイメージさせるビデオ映像が投影されている。
体育館を抜けると、長い廊下。
壁には真っ黒な画面の額縁がたくさん並べられている。
この額はどうしても塗りつぶされた肖像写真を想起させる(これまで効果的に肖像写真を用いてきたボルタンスキーがこのようなことをするとは、その真意が気にかかるところ)。
廊下の突き当たりには大きな換気扇がゆっくり回転しており、その向こうから強烈な光が漏れている。
観客はその光に向かって、しばし歩みを進める。
歩みを進めるとともに大きく耳に入ってくるのは、心臓の鼓動を思わせる音。
心拍音は、2階で最大となる。
音源のある部屋では、鼓動に合わせて裸電球が明滅している。
2階の奥では、壁が取り払われた教室で机や椅子がうず高く積まれ、そこにシーツと映像投影。
3階が最後の作品となる。
ここではフロア全ての教室の壁を取り払われ、蛍光灯の入ったガラスケースと白いシーツが床に並ぶ。
剥がされた黒板の上には、「本を開けばみんな友だち」の張り紙だけが残される。
どうしてもガラスケースは棺桶、シーツは降り積もる雪をイメージさせる。
観客は、この作品を見た後、再び長い廊下と体育館を抜けて出口に戻る。
************************
このように、今回の作品はこれまでのボルタンスキー作品と少し趣が変わっていました。
少なくとも「夏の旅」では、虚構にせよかつてあったものを再現、再構成しようとする意図が強く感じられたのですが、今回の「最後の教室」は、そういった部分が少なかった、というよりも廃校を利用して、何か未知の体験が出来る装置を作り出したかったのではないかという気がしました。
それもかなり荒っぽい手つきで。
今回は舞台美術をやっているJ.カルマンのせいか、一層シアトリカルな内容になっていることも大きな要素です。
作品は、観客が移動することで舞台転換する演劇装置の趣がありましたし、また個々の仕掛けそのものも、ブレードランナーとかの映画のセットのような感じがしました。
なんだかこの学校で、以前にとんでもない大事件でもあったのかという既視感を抱くほどでした。
おそらくは、従来の「情感に訴え、観客を泣かせる」手法は前回の「夏の旅」でやりつくされたので、今回は、何かの再現・再構成ではなく、ここにある痕跡のはらんでいる可能性を増幅し、簡単には受容しがたい得体の知れない巨大作品をつくる方向性にシフトしたのだと思います。
それはそれで理解できます。
ただ、前作よりも一般受けする作品ではなかったように思いました。
僕自身は、今回の「最後の教室」は前作「夏の旅」の存在を前提にし、そこから続く一体的な物語の終章をこのような「観客に受け取り方を任せる」エンディングで締めくくったのだと理解しています。