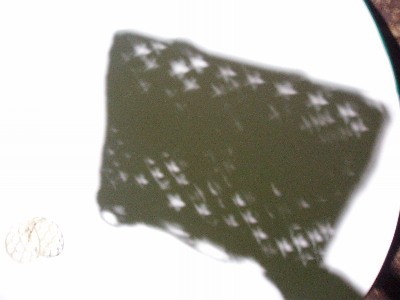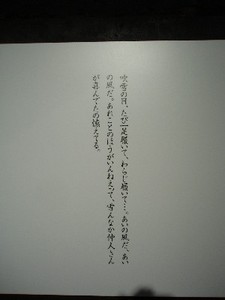印象に残った作品⑦
2009年09月23日 大地の芸術祭
瀧澤潔の「津南のためのインスタレーション-つながり-」も見応えのある力作でした。特に会場2階のテグスの集積による白い空間は迫力がありました。
会場は津南町中心部のかつての機織り工場跡地です。工場跡地であることは、かつてここにあったひとつの産業が失われたことに他ならないので、空家同様、わびしさや悲しさを醸し出すものですが、作者はこの奥行き40mもの大空間を、雪解けの歓びを表現するという「明」と「暗」をテーマにしたインスタレーション空間に変容させました。

まず1階ですが、ここは「暗」の部です。暗闇の中の長細い空間に古着のTシャツが照らし出され浮かんでいます。闇に閉ざされた空間にうごめく人の幻影のようにも見えます。一番奥のつきあたりには無数のワイヤーハンガーがつるされており、吹き抜け空間を経て上の階へとハンガーの連なりが続いていました。
印象に残った作品⑥
2009年09月21日 大地の芸術祭
Earthscapeのメディカル・ハーブマン・カフェ・プロジェクトも印象に残った作品でした。これはボルタンスキーの廃校のグランドで展開している作品で、写真のように人の形をした花壇「メディカル・ハーブマン」に様々な薬草が植えられています。
印象に残った作品⑤
2009年09月19日 大地の芸術祭
印象に残った作品④
2009年09月18日 大地の芸術祭
印象に残った作品③
2009年09月17日 大地の芸術祭
印象に残った作品②
印象に残った作品①
2009年09月16日 大地の芸術祭
雪がない! (繭グッズ講習会)
2009年02月15日 大地の芸術祭, 繭人形/マユビト, 里山のくらし
2月14日、15日と蓬平を訪れましたが、この時期にしては異常なほど雪が少なかったです。
平年であれば2mほどは積もっているはずが、ところどころで地面が露出しており、既にフキノトウが顔を出している始末。
雪は少なければ少ないで、田んぼの水不足など悪影響もあるみたいで、集落の方々も心配顔でした。
明日から少しは雪が降るようなので、それに期待するしかないようです。
さて、今回の現地行きは、ひとつには繭人形「マユビト」づくりの講習会でした。
主にはマグネットタイプの制作確認でしたが、すでに集落のお母さん方はかなり上達されておられ、また楽しんで作って下さっている様子で、有り難かったです。
まだ、一部手直しが必要なものもありましたが、解決できると思います。
皆さんからパッケージデザインなどに積極的な意見も出て、よい雰囲気です。
ちなみにパッケージの絵柄はマユビト図鑑のイメージでデザイン化することになりそうです。
今回の宿泊は、松之山の元三省小学校でした。
2006年に改装されて宿泊所としてオープンしたこの施設は、これまでの学校体育館などでの寝泊まりに比べると天国のように快適なところです。
ベットこそドミトリー形式ですが、全般的に清潔でトイレもウォシュレットです。
写真は食堂の風景。この晩はこへび隊数名のほか、2006年からお世話になっている「ふるへび」の市橋さん、そして団体客30名が宿泊しており、とても賑わっていました。
また、2006年の人気作品「星の木漏れ日プロジェクト」の木村崇人さんも一緒でした(手前の藤色のシャツの人)。
今後はさらに作家やこへび隊の出入りが多くなり、いよいと芸術祭本番の雰囲気になっていきそうです。
ちなみにこの写真は、現在木村さんが制作中の「かざみどり」です。
1週間後の冬のイベント用に、農舞台の正面のカバコフの棚田に設営しています。
たくさんのベニヤの雁が風の向きにきちっと頭を揃えて雪上に群れるという、明快なコンセプトの作品です。
ただ、今年は異常に雪が少なく、地肌があらわになっており、木村さんも困っておられました。
本当に雪が降って欲しいところです。きっと素敵な作品になるでしょう。
好きな作品3 ボルタンスキー
2006年10月15日 大地の芸術祭
クリスチャン・ボルタンスキーは、第1回以降、大地の芸術祭へ継続的に参加しています。
そもそもぼくが前回の第2回で初めて大地の芸術祭をを見に行こうと思ったのも、J.タレルとともにボルタンスキーが出品していると聞いたからです。
二人ともぼくが大好きな作家です。
特にボルタンスキーは、1990年に水戸芸術館での展覧会が素晴らしく、その後、ぼく自身も制作面で影響を受けたことは間違いないと思います。
1990年の展示は、古着のインスタレーションとともに、どこの誰とも知れぬ肖像写真の群像を祭壇のようにして祭り上げ、ライトアップした「モニュメント」「聖遺物箱」シリーズ、ユーモラスで素朴な人形(ひとがた)の切り抜きを蝋燭やライトで壁に映し出す影絵作品など、そのどれもがその場に立ちすくんでしまうような作品ばかりでした。
ボルタンスキーの作品には、そのどれもに「死のにおい」がします。
死といっても、それは残酷な現実をこれ見よがしに突きつけるようなものではなく、不在そのものをそこはかとなく提示するような手法です。
たとえばぼくたちが大正時代の古いモノクロ写真などを見るとき、「ああ、ここに写ってる大人たちは、もうこの世にいないんだ」と思うことがあるのですが、そうしたまなざしが全作品を通じて存在しているように思います。
作者自身、「自らの幼少期の死」を初期の作品のテーマにしているように、(=子どもとしての自分はすでに死んで失われた)
おそらく否応なしに失われたものに対して目がいってしまう性質があるのでしょう。
ボルタンスキーは、観客を泣かせます。
一見、ノスタルジックで感傷的な素材を選び、「我々は日々死んでいく」「我々は常に何かを失っていく」という事実を提示します。
しかし、そこに提示されている素材は、本当に事実に基づいているかどうかは重要でなく、例えば初期作品「10枚のクリスチャン・ボルタンスキーの肖像1946-1964」では、自分自身と無関係の人物の肖像が、それぞれ同年齢の自己として構成されているといった具合です。
要は観る者が共通して持っている過去の記憶を再構成するための素材であればそれでよいという考え方です。
感傷的な作品に感情移入しているように見えて、実はドライで計算づくの制作態度でもあると言えるでしょう。
前回2003年の作品「夏の旅」は、今回と同じ東川小学校を舞台とした大規模なインスタレーションがジャン・カルマンとの合作により展開されました。
この作品は、まさに前述したボルタンスキー節が満喫できる作品でした。
校舎の玄関にぶら下がる無数のスリッパ、枯れた夏草が敷き詰められた理科室、積み上げられた無数の本の山に掛けられた白いシーツ、そして遠く(音楽室と思われる部屋)から聞こえる、在りし日の音楽の授業の音声(廊下が板で塞がれており、遠目にしか教室が見えないが、無人のピアノだけがかろうじて確認できる)、そこでは「兎追いしかの山・・・」など、すこしあざといぐらいのお涙頂戴の選曲がなされている。
これまで「死」や「不在」をテーマにしていたボルタンスキーにとって、大地の芸術祭は、どうしようもないほどドンぴしゃの舞台であることがよくわかりました。
「夏の旅」は文句なく僕の中では2003年のベスト作品でした。
さて、前置きが長くなりましたが、今回の「最後の教室」です。
ここではこれまでとうって変わって、情感めいた手つきが消え、ある意味暴力的といえるほどの大がかりな仕掛けが学校全体に施されていました。
まず、体育館から入ると、床全体に藁が敷き詰められ、むせるような匂い。
高い天井から無数の裸電球が吊られ、それらが扇風機の風で揺らいでいる。
壁面には、雪降りをイメージさせるビデオ映像が投影されている。
体育館を抜けると、長い廊下。
壁には真っ黒な画面の額縁がたくさん並べられている。
この額はどうしても塗りつぶされた肖像写真を想起させる(これまで効果的に肖像写真を用いてきたボルタンスキーがこのようなことをするとは、その真意が気にかかるところ)。
廊下の突き当たりには大きな換気扇がゆっくり回転しており、その向こうから強烈な光が漏れている。
観客はその光に向かって、しばし歩みを進める。
歩みを進めるとともに大きく耳に入ってくるのは、心臓の鼓動を思わせる音。
心拍音は、2階で最大となる。
音源のある部屋では、鼓動に合わせて裸電球が明滅している。
2階の奥では、壁が取り払われた教室で机や椅子がうず高く積まれ、そこにシーツと映像投影。
3階が最後の作品となる。
ここではフロア全ての教室の壁を取り払われ、蛍光灯の入ったガラスケースと白いシーツが床に並ぶ。
剥がされた黒板の上には、「本を開けばみんな友だち」の張り紙だけが残される。
どうしてもガラスケースは棺桶、シーツは降り積もる雪をイメージさせる。
観客は、この作品を見た後、再び長い廊下と体育館を抜けて出口に戻る。
************************
このように、今回の作品はこれまでのボルタンスキー作品と少し趣が変わっていました。
少なくとも「夏の旅」では、虚構にせよかつてあったものを再現、再構成しようとする意図が強く感じられたのですが、今回の「最後の教室」は、そういった部分が少なかった、というよりも廃校を利用して、何か未知の体験が出来る装置を作り出したかったのではないかという気がしました。
それもかなり荒っぽい手つきで。
今回は舞台美術をやっているJ.カルマンのせいか、一層シアトリカルな内容になっていることも大きな要素です。
作品は、観客が移動することで舞台転換する演劇装置の趣がありましたし、また個々の仕掛けそのものも、ブレードランナーとかの映画のセットのような感じがしました。
なんだかこの学校で、以前にとんでもない大事件でもあったのかという既視感を抱くほどでした。
おそらくは、従来の「情感に訴え、観客を泣かせる」手法は前回の「夏の旅」でやりつくされたので、今回は、何かの再現・再構成ではなく、ここにある痕跡のはらんでいる可能性を増幅し、簡単には受容しがたい得体の知れない巨大作品をつくる方向性にシフトしたのだと思います。
それはそれで理解できます。
ただ、前作よりも一般受けする作品ではなかったように思いました。
僕自身は、今回の「最後の教室」は前作「夏の旅」の存在を前提にし、そこから続く一体的な物語の終章をこのような「観客に受け取り方を任せる」エンディングで締めくくったのだと理解しています。
子どもにも大人にも人気があった作品
2006年10月07日 大地の芸術祭
前に紹介した「ブランコはブランコではなく」や「レインボーハット」とともに、子どもに人気があった作品を紹介します。
これは木村崇人「星の木漏れ日プロジェクト」です。
写真は昼間のように見えますが、夜の9時頃。
実は森の上にクレーンで巨大な発光体が吊されています。
木々の隙間からの木漏れ日をよくみると、全て☆型です。
実は光源自体が☆型をしているわけです。
編み鞄をかざすと、ご覧の通りです。
子どもはもちろん、おとなも無邪気に楽しめる作品でした。
また、それとともに自然科学的な視点から「不思議」を体験できる作品でもありました。
この作品は、必ずしも越後妻有の地域性に根ざしたものではありませんが、
やはりこれだけ大規模な仕掛けとなると、このような大イベントでしか実現できないのでしょうね。
これは十日町の中心街にあったレアンドロ・エルリッヒの「妻有の家」。
水平に置かれた建物の外壁が、斜めに立てかけられた巨大ミラーに写って、
まるで実際に家が建っているように見えます。
写真は、ええ歳したおじさんが遊んでいる様子。
この作品でも大人が童心に帰ってしまいます。
敢えて古民家ではなく現代の妻有の建物の特徴をコラージュした外観としています。

これは同じ作者の金沢21世紀美術館での作品。
これもちょっとした視覚上のトリックで、人を驚かせる作品です。
我が家でも前回、今回の大地の芸術祭は家族で見に行きましたが、
この手の作品は子どもを飽きさせないためにも有り難かったです。
こういった作品に代表されるように、大地の芸術祭では、サービス精神や娯楽的要素がある作品が多かったです。
全てが全てこうした作品ばかりでは、アートの遊園地みたいになってしまって、さずがに芸術祭としてはまずいですが、
傾向としては「わかりやすい」「明快な」「シンプルな」作品が多かったです。
菊池歩の「こころの花」(ビーズでつくった3万個の花)などはその典型でした。
人気があった作品にはそうしたものが多かったように思います。
話はやや脱線しますが、
大地の芸術祭では、いわゆる銀座や西天満の「現代アートのけもの道」でしか通用しない類の作品は少なかったです。
思うに、これはやはり制作時における場所性の違いというのが大きいと思われます。
都心の画廊とは違って、大地の芸術祭では人の土地で、住民の協力を得ながら制作を行う。
必然的に(意識するしないにかかわらず)作品は社会とつながらざるを得なくなる。
ひとりよがりな作品、住民にどう見られるかを全く意識しない作品が生まれる余地は少ないのです。
その結果、作品に間口の広さが生まれ、普遍性を獲得し、
普段現代アートに詳しくない方でも十分に楽しめる作品が次々と生まれていったのではないでしょうか。
一方では、大地の芸術祭の作品完成度のばらつきや、作品が分かり易すぎる、迎合的だとか安易だとかという批判も聞きますが、
ともすれば我が道を行きがちな現代アーティストがこんなに風に変われるなんて、感動的だと思いませんか。
この芸術祭自体が、アーティストの社会化訓練の場でもあったわけです。
このあたりにも、都市の現代アートが抱えている問題点と社会性の獲得に向けたヒントが隠されているような気がします。
全体の傾向として、作家がこれまでやってきた制作手法や方法論をそのまま持ち込んだだけの作品よりも、
越後妻有で展示するために一度白紙から方法論を考え直した作家の作品の方が、
断然、普遍性があり、現地の社会の中での強度があったように思いました。
(なお、今回から文体を丁寧語に戻しています。なんだか偉そうだったので・・・)
好きな作品2
2006年10月01日 大地の芸術祭
作品ナンバー208(うちのお隣の作品)で、斎藤美奈子「メモリー-田野倉プロジェクト」。
これも空き家プロジェクトで、茅葺きのいかにも古民家らしい家屋をまるでギャラリーのように美しく整備し、そこに集落のおばあちゃんたちが嫁入りの際に見たであろう風景の写真と、彼女たちの言葉を併置する。
写真とテキストを併置するやり方はよくある手法ながらも、集落のおばあちゃんを丹念に取材し、彼女たちのこころのひだに寄り添うようなまなざしを感じる。なんでもない普通のおばあちゃんの人生だって、立派に感動的な作品になりうること自体が、感動的であり、また、その人生を見守ってきた風土や家が観る者の周囲にあることから生じる説得力がさらに作品を印象的にしていた。
個人的には、当事者たちのポートレイトは敢えて用いず、「彼女たちが見たであろう風景」のみに絞った方が良かったとも思うが、それでも、作者の人間を見るまなざしの暖かさ、写真のクオリティの高さなど、忘れることのできない作品だった。
好きな作品1
2006年09月30日 大地の芸術祭
前回はあまりに力こぶを入れた文章をかいてしまって、あとで読んでみると恥ずかしかった。
まだ芸術祭終了の興奮覚めやらぬ時期だったので、お許しください。
そこで、今回はもっと気楽に、今年の芸術祭で気に入った作品を何点か紹介したい。
まずは半田真規「ブランコはブランコではなく」。
太く長い竹を組んだだけのブランコであるが、中里地区の清津川流域の絶妙なポイント(田んぼや神社など)に20基設置されている。
ブランコで風切るのはいくつになっても楽しいこと。
それが田んぼの上であったり、広大な河岸段丘風景であったりすると、さらに気持ちいい。
作家のロケーションを見る目(何をみせたいか)が作品の重要な要素である。
造形的にも祭りなどでよく見る竹の組み方をイメージさせ、とても土俗的で興味深い。
実は最初は、ときどき見かけるこども受け狙いの作品かと思ったが、全然そんなことなく、大人も子どもも楽しめる秀作でした。
続いては古郡弘「みしゃぐち」。
前回の芸術祭で住民と共にたんぼの土を積み上げて砦のようなランドアートを築いた作者が、今回は同様の路線ながらも、さらに建築的な作品をつくりあげた。
泥捏ね、土遊びと言えば、手仕事のスケールであるが、それが巨大な塊となった驚き。
オブジェとか、彫刻とか、建築とか、そういうカテゴライズについて考える意味を失わせるほどの迫力があった。
沖縄の斎場御嶽(せーふぁーうたき)にも通じる場の力を感じさせる作品。
(みしゃぐち遠景 小高い丘のような外観)
(みしゃぐち内部 ぐるりと回廊に囲まれている)
(みしゃぐち内部 回廊の中央は屋根がない)
関口恒男「越後妻有レインボーハット」。
森に囲まれたキャンプ場の一角に現れたわらぶき屋根の小屋。
手前の池には鏡が沈められており、そこに差し込んだ日光が反射して小屋の天井に虹を映し出す。
小屋の中には、インドのゴアなどを渡り歩いたという関口さんが太鼓を叩き、歌を歌い、レイブパーティーを開く。
関口さん本人とは、会期前、よく宿舎で一緒になり、お話もしたが、すごく穏やかで魅力的な人だった。
会期中は全ての日に現場におられて、鏡の角度を調整されていたとのこと。
最後のピースが嵌め込まれると、電流が走る
2006年09月16日 大地の芸術祭
大地の芸術祭は、参加したぼくにとって、これまでにない新鮮な体験だった。
これまでぼくが何度となく都会で開催した、どの展覧会とも違う反応がそこにはあった。
どうして大地の芸術祭は、あそこまで魅力的だったのか。
都心から何時間もかかるあのような山奥に、なぜ30万人の人が押し寄せたのか。
美術ファンのみならず普段、現代アートに縁のない人たちにどうして受け入れられたのか。
本欄はそんなことを考える「大地の芸術祭論」としたいところであるが、そこまで大上段に構えるのも荷が重いので、「大地の芸術祭あれこれ」と題して、時々思い起こしたことを書き連ねようと思う。
まずは、この写真を見て欲しい。
これは今回の芸術祭の目玉だった、クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマンの「最後の教室」の1室。
廃校になった校舎全体をつかった大規模なインスタレーション作品である。
棺桶のようなガラスケースが並べられた白く清浄な空間。
一番奥の壁面には、剥がされた黒板の跡と、意図的に残された張り紙「本をひらけばみんな友だち」が。
遠くから聞こえる心臓の鼓動音とも相まって、見る者の胸を揺さぶる。
大地の芸術祭の作品が、通常の美術展と大きく異なるのは、このような「場の記憶」と密接に結びついた作品が多かったことである。
普段我々が美術館で作品を鑑賞する行為は、作品を虚構として了解することを前提としている。
多くの美術作品は(ドナルド・ジャッドの「特殊な物体」的なコンセプトの作品を除いては)何かを再現したり、作者の内面の世界を表現したものである。
少なくとも作品は、美術館という制度枠の中で、外界から切り取られて屹立している。
見る側は、特に意識することなくその制度を了解し、ちょうど動物園で虎の檻や、アシカのプールをのぞき込むようにして、作品を見ている。
しかし、大地の芸術祭は、サファリパークなのだ。
大地の芸術祭に参加する作家は、まず作品が置かれる場を読み取ろうとする。
そこで語られるべき記憶、歴史、人々の思いを丹念に発見していく。
ボルタンスキーの場合は、学校だった。
そこでかつて繰り広げられた、喧噪、笑い声、胸のときめき、仲間たちの存在。
私の場合は、蓬平集落の一時代を支えた養蚕業だった。
つらい桑取り、いやな臭い、蚕の成育の心配、美しい絹糸、自分で織った花嫁衣装。
国の農業政策によって切り捨てられ過疎化に歯止めがかからないこの地方には、語ってもらいたがっている地域の記憶、我々が昔持っていたはずの日本の原風景とでも言うべき記憶が無数にある。
作品は、そうした「うち捨てられようとしている場の思い」を顕在化させるきっかけであることが多い。
作品というピースが、場に嵌め込まれたとき、明らかに電流のようなものが走って、空間的・時間的に場全体に生命がみなぎる。
作品効果の及ぶ範囲(観る者が作品を通じて想起する範囲)は、現場である古民家や廃校を遙かに超え、集落全体、そして遙かな過去へとひろがっていく。
作品はただの切り取られた表現ではなく、観客が今いるその場全体を作品世界へとつなげていく。
それが大地の芸術祭の魅力なのだ。
(写真=繭の家-養蚕プロジェクト 作品C「雲の切れ間から」 小箱の蓋を開けると真綿と繭でつくられた蓬平の景色が広がる)